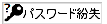時空 解 さんの日記
2017
10月
19
(木)
10:29
本文
皆さん、おはようございます。時空 解です。
昨日は失礼いたしました。時間が取れませんでした。
昨日は失礼いたしました。時間が取れませんでした。
さて、土曜日に図書館で借りて来た「文体練習:レーモン・クノー、朝比奈弘治 訳」を一通り読みました。まだ "訳者あとがき" は読んでいないのですが、それはさておき、自分の想った感想をさっそく書いてみます。
はじめに、この書籍の前評判を読んで想った事は「事実はどうなんだろう?」と言う点でした。
同じ1つのストーリーを99個の文体で描いてあると言う事から、その小さな1つのストーリーは99個の中で全て正しく描かれているのだろうか?一致したストーリーなのか?、と空想を広げたのです。
書籍を読み始めるに当たって、このように空想を広げて読み始めるのは良い事ではないかも知れませんね。書籍に先入観を持つ訳ですから…。
しかし、そのせいでこの書籍にハマった感があります。もしかしたら、この書籍の狙いは、まさに "読者から空想を引き出す" と言うところにあるのかも知れません。文章遊びを含むこの書籍は、原書はフランス語で書かれています。ウィキペディアのよると、なんと31もの他言語に翻訳されています。大して仕掛けの無い1つのストーリーが世界中で愛されている理由は、きっと空想を引き出す魔力にあるように思えました。
同じ1つのストーリーを99個の文体で描いてあると言う事から、その小さな1つのストーリーは99個の中で全て正しく描かれているのだろうか?一致したストーリーなのか?、と空想を広げたのです。
書籍を読み始めるに当たって、このように空想を広げて読み始めるのは良い事ではないかも知れませんね。書籍に先入観を持つ訳ですから…。
しかし、そのせいでこの書籍にハマった感があります。もしかしたら、この書籍の狙いは、まさに "読者から空想を引き出す" と言うところにあるのかも知れません。文章遊びを含むこの書籍は、原書はフランス語で書かれています。ウィキペディアのよると、なんと31もの他言語に翻訳されています。大して仕掛けの無い1つのストーリーが世界中で愛されている理由は、きっと空想を引き出す魔力にあるように思えました。
「事実はどうなんだろう?」と考えながら読み始めて最後99個目を読み終えると100個目も読んでみたくなります。でもそれが無いんですよね、残念です。
これがこの書籍の究極の感想ですかね。
これがこの書籍の究極の感想ですかね。
"実際のストーリー = 事実" を紐解くに当たって、まず注目したのは観察眼と主眼です。
観察眼とは観たことを伝えている文体のことです。対して主眼とは観察された本人の文体です。
この2つに注目して99個を読んでみると、文体は「観察眼:96」「主眼:2」「どちらでもない:1」に分類できるでしょう。
1つだけ「どちらでもない」と分類したのは、最後の99個目の文体が特殊だからです。ここに文字通り最後の仕掛けがあるので、他の98個とは区別したいところです。実際にガラリとスタイルを変えて来ます。
観察眼とは観たことを伝えている文体のことです。対して主眼とは観察された本人の文体です。
この2つに注目して99個を読んでみると、文体は「観察眼:96」「主眼:2」「どちらでもない:1」に分類できるでしょう。
1つだけ「どちらでもない」と分類したのは、最後の99個目の文体が特殊だからです。ここに文字通り最後の仕掛けがあるので、他の98個とは区別したいところです。実際にガラリとスタイルを変えて来ます。
ともかく「事実はどうなんだろう?」と考えながらストーリーを分析して行くと、じつは事実なんて明確にはならないことが分かります。事実を推測するに当たっては、目撃者よりも当事者の言葉の方が重要な訳で、つまり主眼で書かれている文体の内容を優先して考えるべきだと思うのですが、その当事者の言葉も両者で食い違っていますからね。
この食い違いこそが事実…現実 (?) と言えば言えますけどね。ここがレーモン・クノーが創り上げた大きな魔力の1つでしょう。事実はすべての人が納得のゆくようには紐解けない、と言うところでしょうか…。
この書籍の99個の文体の基準となるストーリーは、いやがおうでも1つ目、" 1. メモ" と言う文体に書かれている内容になります。読者が一番始めに読む文体ですからね。ここから基本のストーリーは、バスの中の出来事と2時間後に公園で見掛ける出来事、この2つで構成されている事が直ぐに分かります。登場人物は、バスの中を若者:Y君と初老:O氏とすると、2時間後の公園での登場人物は若者:Y君と紳士:T氏となります。
2つの場面に出てくる若者が、両方同一人物だと言うのもこの書籍の仕掛け・魔力の1つです。
この食い違いこそが事実…現実 (?) と言えば言えますけどね。ここがレーモン・クノーが創り上げた大きな魔力の1つでしょう。事実はすべての人が納得のゆくようには紐解けない、と言うところでしょうか…。
この書籍の99個の文体の基準となるストーリーは、いやがおうでも1つ目、" 1. メモ" と言う文体に書かれている内容になります。読者が一番始めに読む文体ですからね。ここから基本のストーリーは、バスの中の出来事と2時間後に公園で見掛ける出来事、この2つで構成されている事が直ぐに分かります。登場人物は、バスの中を若者:Y君と初老:O氏とすると、2時間後の公園での登場人物は若者:Y君と紳士:T氏となります。
2つの場面に出てくる若者が、両方同一人物だと言うのもこの書籍の仕掛け・魔力の1つです。
さて、この基本の状況が頭に入ったところで書籍を読み進めて行くと、主眼で書かれている2つの文体が14番目と15番目に出て来ます。バスの中での出来事を、その本人2人がそろって証言する形になるのですが、その内容の歯がゆいズレが絶妙です。同じ状況を当事者2人が説明する訳ですから、本来ならば内容は一致するはずなのですけどね。
これで気になり出すのが、次の場面の登場人物、公園に現れるT氏についてです。しかしこのT氏が語る主眼的な文体は最後まで出て来ません。
しかし最後の99個目の文体でT氏は顔を出すのです。でも、ストーリーの事実がどんなだったのかは、まったく持って分かりませんけどね。ここで見事に、この世の中に現存する事実がどんなものなのか、それがパッケージングされる瞬間を読者は見せられる ( 魅せられる? ) ような気がするのですが…。
皆さんはどんな感想を持つでしょうかね?「文体練習 」
」
この書籍はいささか特殊過ぎますが…でもいちどは図書館で読んでみてはいかがでしょうか。
しかし最後の99個目の文体でT氏は顔を出すのです。でも、ストーリーの事実がどんなだったのかは、まったく持って分かりませんけどね。ここで見事に、この世の中に現存する事実がどんなものなのか、それがパッケージングされる瞬間を読者は見せられる ( 魅せられる? ) ような気がするのですが…。
皆さんはどんな感想を持つでしょうかね?「文体練習
この書籍はいささか特殊過ぎますが…でもいちどは図書館で読んでみてはいかがでしょうか。
では今日も1日を始めます。
応援してね。
千里の道も一歩から。そしてその道は登り坂です。ローマは1日にして成らず、です。
(ポチッとブログ村のバナーをクリックしてね)![]()
| 項目 | 昨日の実施状況 | 今日の予定 |
|---|---|---|
| ブログを更新 | 10時00分 | 8時30分 |
| そろばんの練習 | できず | 30分 |
| 数学の学習 (青チャートI+A ) | p190 | p191 ~ p193 |
| 数検の学習 ( 白チャート II+B ) | p206 終了 | p207 ~ |
| + α 学習( LaTeX2ε 、コンテンツ作成など ) | 「文体練習」アマゾンレビュー下書き完了 | アマゾンレビュー |
閲覧(7690)
| コメントを書く |
|---|
|
コメントを書くにはログインが必要です。 |
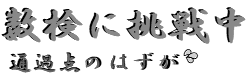




 前の日記
前の日記